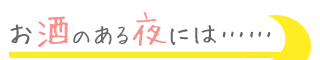

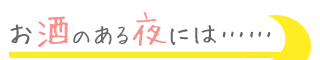

……そういう内容を舞が理解するまでに、実に一時間かかった。話をしながら怒りがふつふつとこみあげてくるのか、ユリは、陽気な彼女にしては極めて珍しく、話の端々で荒れに荒れまくった。
「だーれが、兄離れもできない甘えん坊じゃー!」
とか、
「口が立つからって、偉そうにするんじゃねー!」
とか、グラスを振り回しながら大声で喚き散らした。
年少の友人の荒れ様を見ながら、キングはため息をつきながら肩をすくめるだけだ。ユリが振り回しているグラスは、19世紀半ばに作られた貴重品なのだが、それも無事に帰ってくるかどうか。ここまでユリが荒れることが分かっていれば、渡すこともなかったのだが……。
舞は、キングが自分を呼んだわけをよく理解した。キングは自身がドライな性格だけに、こういう湿りきった話題が苦手なのである。こういう話に慣れているのは、結局、舞なのであった。
舞の偉いところは、ユリの話の最中に、無用な意見を挟まないところだ。
「それは違うんじゃない?」
とか、
「こうしたほうがいいと思うんだけど」
などとは、舞は言わない。ひたすらユリが話したいだけ話させておいて、自分は軽く相槌を打つだけである。
この場合、ユリは人の意見を聞きたいわけではなく、ただひたすらストレスを発散したいだけなのだ。そのユリの心境が、舞にはよくわかっている。
舞がしなくてはならないのは、その暴れるような話を、上手く、穏やかに収束させることであるが、それも難しいことではない。
ユリの場合、幸いにも根が陽性である。一度たまったものを全て吐き出してしまえば、ストレスの全てが解消されなくても、ある程度は復活できるであろう。
無論、舞はこの無邪気な友人のために、ユリの兄のリョウ・サカザキに対しては、一言、口ぞえする気でいる。
ユリが、マシンガンかロデオか、と言わんばかりの文句と非難の嵐を一通り吐き出し終えたのは、それから更に30分後である。いったん口をつぐんでカクテルを一気にあおると、それまでの騒ぎがまるで嘘のように、ユリはカウンターに突っ伏して寝息をたて始めたのだ。
今まで飲んでいたのは、シャンパンとオレンジジュースをビルドしただけの「ミモザ」で、はっきり言ってしまえばアルコール初心者用の軽いカクテルなのだが、それでもユリは眠ってしまう。その酒に弱い、という自分の体質を、急に思い出したようであった。
キングが恐る恐る、その手から高級グラスを奪還すると、まるで誘拐犯から解放されたわが子をいつくしむように抱え込んでから、そっと棚に戻した。
「それにしても、見事な暴れっぷりだったね」
舞に慰労のカクテルを出しながら、キングは苦笑した。今夜、舞に出すお酒は、すべて奢りである。キングなりの感謝のかたちだった。
「あのユリがねえ。ここまでストレスを抱え込むなんて、よっぽどのことだったんだろうな」
そっと優雅にグラスに口をつけながら、舞は妖艶に微笑んだ。憧れこそすれ、ユリには決してまねのできない仕草である。
舞が飲んでいる「サムライ」は、日本酒をベースにしたカクテルで、そんなにアルコールは強くはないが、すっきりとしたライムが香ばしい。日本人の舞のために、キングが気を利かせたのだろう。
「明るい性格だから勘違いされやすいけど、ユリちゃんは基本的に受け身の
舞の何気ない一言が、ユリ本人も気付き得ない本心を表しているように、キングには思えた。
ユリは弱い自分、護られるだけの自分から、必死に脱却しようとしている。けれど、苦難のなかで定着してしまった性格というものは、自分で直そうとしてもなかなか直るものではない。
兄に心配をかけたくない、というユリの人格の根っこの部分は、もう固定されてしまっている。結局、兄の心配に繋がりそうな要素を、本人も気付かないうちに、すべて自分のうちにしまいこんでしまうのだ。
それがたまりきってしまうと、今日のようになってしまうのだろう。
もっとも、今回の「爆発」は、オーガスタ・ジュールズという外部要因が、堪忍袋の導火線に火をつけてしまったことが原因で、ユリ自身に責任を押し付けるのも酷というものであるが。
舞はすっかり寝入ってしまったユリの頭を撫でながら、軽くため息をつく。
「別に、そのジュールズとかいう女の人に同意するわけじゃないんだけどさ」
「うん?」
キングがカウンターに肘を着いて興味を示した。
「今回はユリちゃんも大変だっだけど、もしもリョウさんが結婚でもすることになったら、その奥さんも大変だろうなーって思っちゃうな」
「どういうこと?」
「なんだかんだ言ったところで、リョウさんとユリちゃんが仲が良いことは、事実なわけじゃない?
もちろんそれはそれで良いことなんだけどさ、もしも私がリョウさんと結婚するとしたら、すごく複雑な気分になると思うよ。
妻としては、最愛の旦那様にまず自分のことを見て欲しいし、気にかけてほしいのに、常に私とリョウさんの間には、ユリちゃんがいる。でも二人にとってはそれが自然なことで、悪気があるわけじゃないから、文句も言えない。
ユリちゃんが明るければ明るいほど、リョウさんが誠実であればあるほど、自分は苦しくなっていくと思う」
もしも私がそういう立場ならね、と加えて、そっとグラスを置いた。
「そんなものなのかな」
と、キングは言葉を濁した。そういう心境がわからないわけではないが、なるべくならそんな話題には足を突っ込みたくなかったのだ。
しかし、舞はそんなキングを話題から逃すまいとして、話を続ける。
「……と、私は思うんだけど、キングさんならどう?」
「私? 私に聞かれてもね。別に私がリョウと結婚するわけじゃなし、ユリの話し相手くらいにはなってあげられるけどさ」
「……今日、そのユリちゃんの話し相手のことで私に泣きついてきたのは、どこの誰でしたっけ」
「忘れたね」
強引に話を切って立ち上がったキングの背中に、舞は言葉を投げかけた。
「噂に聞けば、ユリちゃんのお父さんのタクマ師が、色々と暗躍してるって話だけど?」
ピクリとキングの動きが止まる。
タクマ・サカザキは、どうもリョウの嫁にキングを、という考えがあるらしい。ことあるごとに、それっぽい話をあちこちで吹聴しては、当のリョウとキングの眉をひそめさせていた。
舞としては、キングが慌てふためくか、それに近い派手なリアクションを期待したのだが、キングは背中を向けたまま、大きくため息をついただけだった。
「その話か。それには、私もリョウも困惑してる。
タクマがあの性格だから、人の話なんか聞きゃあしないが、私らにとってはありがた迷惑なのさ」
肩をすくめておいて、キングは自分用のカクテルをグラスに注いだ。その表情からは、その言葉が真実であることが見て取れる。
「キングさんも、リョウさんとは仲がいいでしょ? 好きになったり、なんてことはないの?」
「ないね」
きっぱりと、そして即座に、キングは言った。舞はその断言ぶりに、思わず首をかしげる。
「それって、リョウさんのことを異性として意識できない、ってこと?」
「蹴るよ?」
ムエタイの達人に本気で凄まれて、舞は慌てて頭を振った。
さすがにキングに本気でキックを叩き込まれたら、舞とて無事には済むまい。
キングは三白眼で舞をひと睨みし、自分のグラスをあおった。
「確かに、リョウはいい男さ。人間として、私が尊敬できる男は滅多にいない」
キングは数秒間、天井を見上げて、言葉を続けた。
「でも、私とあいつじゃ無理だ。よしんば、ほかの男と結婚する可能性はあっても、リョウとだけはないね」
またしても、キングは断言する。
舞には分からない。
キングは、リョウのことを嫌っているわけではない。このプライドの高い女傑が、人間としては尊敬できる、とまで言い切っている。
それだけ、彼女の中でリョウ・サカザキという人間の評価は高いのだ。
ならば、なぜそれほどまでに彼との未来を拒絶するのか。それが絶対に真実になるとは、誰も思ってはいない。たかが仮定の話ではないか―――。
舞の表情から彼女の心奥を覗いたのか、キングはため息をついた。
無言で突き放してもいいのだが、ユリの話し相手をしてくれた借りもある。
キングは、低く語った。
「私とリョウは、似すぎているんだよ」
「似すぎてる?」
「そう。お互いの過去が、ね」
キングのグラスのロックアイスが、静寂な空気を揺らしてアルコールに溶ける。
一瞬の空隙を置いて、キングは続けた。
「細かい差異はあるが、私もリョウも、戦う動機は同じだった。戦い続けた年数も時期も、ほぼ重なる。そんな生活から脱却できた時期まで同じだ。
それはまるで、両合わせの鏡のようなものさ。共感できる部分も多大にあるけど、それだけに、見えなくてもいいものまで見えすぎる。
お互いの妹や弟に隠しておきたいこと。それに、拭えないほどの血に塗れた拳のこと……。思い出したくないことまで、全部、見えてしまうんだ」
キングはグラスを傾ける。そして、温度の高い吐息。
「共感だけじゃ、人間は一緒にはなれない。昔から言うだろう? 向かい合わせた鏡から出てくるのは、悪魔だけなのさ」
重い。舞にとっては、重い言葉。そして、重い関係だった。
キングとリョウの過去には常に、血と死の臭いがついてまわる。他人と自分の死が、常に二人の足元には口を開けていた。いつ、そこに放り込まれてもおかしくないほどの近さで。
それは、現在の二人の涼やかな人格からは、にわかには信じられないほど、深く、濃い闇を、二人の精神の奥地にはびこらせている。
―――見えなくてもいいものまで見えすぎる。
―――思い出したくないことまで、全部、見えてしまう。
それが、どれだけに苦しみを二人に与えるのか、舞には想像がつかなかった。
この尊敬できる友人の闇を、初めて覗いた気がした。
「……ごめん」
それだけを、舞はつぶやいた。
「さて、寝つぶれてしまった酔っ払いもいるし、今日はもう店じまいだな」
キングは声のトーンを上げて、勢いよく身体を上げた。
店じまいも何も、扉には「CLOSED」の札がかかったままなのだが、今日はもう、他人のために営業する気もない。友人たちのための貸しきりだ。
語れるだけ語って、語りつくしたら店じまい、そんな日があってもいいかもしれない。
キングは、無言のままうつむき気味にグラスを傾けている舞の肩を、一つだけ叩いた。
その表情は、いつものクール・ビューティーと称される顔よりも、もう少し穏やかだった。
「確かに、過去を思い出すのは辛いかもしれないけどね。
だけど、私たちは失うばかりじゃなかった。むしろ、得たものの方が多かった。
失ってしまったものと比較することはできないけど、得たものも、凄く貴重で大切なものさ。
たとえそれで傷つくことがあったとしても、それは色々なことを教えてくれる。私たちにとって、かけがえのないことを、ね」
それは、たとえばユリにとっての兄との絆。キングにとっての弟との絆。
そして、二人にとっての、大切な友人との絆。失ってはならないものを護るための、強さと覚悟。
それがあったから、ユリはオーガスタの皮肉に、必要以上に耐えなければならなかった。
キングは、リョウに共感し、彼を尊敬しながらも、そこに辛いものも見なければならなかった。
だが、それを知っていることで、彼女たちは人間として、そして格闘家として、他の人よりも一段強い存在でいることができるのだった。
「あんたには感謝してるよ、舞。あんたがいてくれるから、私もユリも、上を見て歩いていける。
私とユリだけじゃ、意識しなくても傷の舐めあいになる。そうならないですむのは、ありがたいことさ、本当にね」
言って、舞のグラスに自分のグラスを軽く合わせた。
舞は無言のまま、少し涙ぐんだ目で、頷いた。
不知火舞にとって、今日は本当に椿事が続いた一日だった。
舞にとっては驚きの連続だったが、悪い意味での驚きは、一つもなかった。
これ以降、舞やユリがバー「イリュージョン」を訪れる機会は、また少しずつ増えていく。
そして翌7月。サウスタウンの極限流空手総本部は、オーガスタ・ジュールズとの契約を解除する旨を、正式にガルシア財団に通告した。
オーガスタがロバート・ガルシアの個人秘書を外され、ロバートの知らないところで極限流本部付きに配属されてから、半年後のことである。
(Fin)
「バー・イリュージョン」シリーズ(今考えた)の三作目。
このシリーズのユリは、酔っ払って文句言ってるだけですね(^^;)。
個人的に、リョウとキングがくっつくことに、少々違和感があったんですが、その理由を考えながら書いたら、こうなりました。
あわせて、ユリとリョウの関係、'94女性格闘家チームにおける舞の存在感を入れてみましたが、そのぶん長くなってしまいましたね。
ミス・ジュールズは、「KOF12」のロバートのストーリーからのゲスト出演です。
少々損な役回りになってしまいましたが、普段、意地悪な女の子を書くことがないので、新鮮な気分で書けましたね。
(初稿:09.07.07)
(しまった、改めて読み返してみたら、これ「お酒のある夜には -Sugar-」とほとんど同じ内容だ(汗))
(09.10.10)