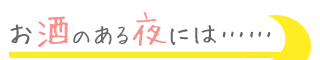

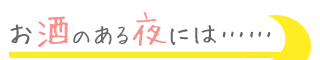

サウスタウンに滞在していたその日、不知火舞は立て続けに珍しい事態に直面していた。
朝にはアンディが自分から週末のデートに誘ってくれたし、昼間にはテリーが昼食をご馳走してくれた。
いずれも、この兄弟にしては滅多に無いことで、言葉を変えれば“珍事”と言ってもいい。
こうなれば夜にも何かあるだろう、と秘かに期待していた。
……確かに、あった。
あったのだが、その発端は舞の意表をつきすぎた。
夕方、けたたましく存在感を主張する電話に出た。
「はい、不知火……」
「しくしくしく……」
いきなり、ぞっとした。
その、すすり泣くような女の声は、舞の背筋に冷気を吹き込むに十分だった。
時は六月だ。一足早い怪談じみたいたずら電話かもしれない。
舞の年少の友人である藤堂香澄ならば、喜んでこれに付き合うのかもしれないが、残念ながら舞には勇んで怪談に付き合うような性癖は無い。
少し鳥肌を立てながら、ゆっくりと受話器を置こうとした、次の瞬間に聞こえてきたのは、彼女の聞きなれた声だった。
「舞……、今から来れるかい? 大丈夫なら助けてくれ……」
【悲鳴】と言うよりも【慟哭】に近いその声を発していたのは、舞の年上の友人、キングだった。
舞が服装と覚悟を整えてキングが経営するバー【イリュージョン】の前に立ったのは、彼女からの電話を受けて20分後、午後七時前だった。
気の知れた友人の店だし、普段なら覚悟など必要とする場所でもないのだが、状況が状況である。
いつものキングは姉御肌で頼りがいがあり、若い世代の女性格闘家たちの相談役、お姉さん役に徹するような女性である。
波乱の人生を歩んできた彼女も、ここのところ生活が安定したせいか、女らしい一面を見せる場面も増えてはいるが、滅多なことでは人前で泣き言を言うような人ではなかった。
間違っても先ほどのように、人に泣きつくような人ではないのである。少なくとも、舞が知っている範囲では。
それが、あのような電話をよこしたからには、よほどのことがあるのだ。
例えば、対立する飲み屋の刺客に毒ガスを撒かれた、とか、店内で百人規模のケンカが始まった、とか。
……舞のほうがよほど失礼なことを考えているようだが、要はそれほどのことでもない限り、キングをあそこまで動揺させることは不可能だ、と舞は思っているのだ。
(警察に連絡を入れたほうがよかったかしら)
慌てていた20分前の自分に少し後悔しながら、それでも動揺はせず、舞は呼吸を整えると、開店前の店のドアを一気に押し開けた。
「キングさん、なにがあっ……て?」
声を張り上げて店に踏み込んだ舞の視神経に飛び込んできたのは、あまりに静かな光景だった。
毒ガスの靄もなければ、ケンカの最中でもない。
そこにいた人物はたった二人。
一人は無論、キングである。彼女は、カウンターの奥で腕を組み、困りきったような顔をしていた。
カウンターに座っているもう一人は、舞に背中を見せていたが、その黒髪と長い三つ編みから女性であると思われる。
そして、舞の友人でこんなに長い三つ編みをしているのは一人しかいない。ユリ・サカザキである。
だが、普段の明るいユリならば、舞の来訪に気付くのと同時に振り向き、大声で彼女を呼んだであろうが、今宵はなんだか様子がおかしい。舞の声を聞いてもぴくりともせず、ただ座っていた。
キングは舞の存在に気付くと、助けが来た、とばかりに彼女をカウンターに手招きした。舞はユリの隣に腰を下ろす。
「いや、突然呼び出して悪かったね」
申し訳なさそうにいうキングに、舞は驚きを治めきれないまま、長身の友人を見上げた。
「いったい何があったのよ。普通じゃない様子だったけど……」
キングは一つ首を振った後、舞にしか分からないように指で示した。
その先にいるのはユリである。そういえば、自分の隣に舞が座っても、ユリは身動き一つしない。
なるほど、普通でないのはキングではなく、ユリの方だったのか。なんとなくそう気付きつつ、舞はユリに話しかけた。
「ユリちゃん、なにかあったの?」
言われて、顔を上げたユリの表情に、舞は思わずたじろいだ。
見たことも無い表情のユリが、そこにいた。
顔が真っ赤になっているのは、したたかに酔っているせいかもしれないが、それにしても目が据わりすぎている。
眉尻はとろんと下がっているが、それでも抑えきれない感情が、その端々に現れていた。
上半身をカウンターにつんのめりながら、チビチビとグラスに口をつけている。
そして、ユリは舞を見上げると、口先をあひるのように突き出して声を上げた。
「なぁにもないモン! ユリは怒ってなんかないもん!」
明らかに呂律が回っていない。悪酔いである。舞は視線をキングに移した。
ユリは酒に耐性が無い。はっきり「弱い」と言い切ってもいいくらいだ。
酔う、ということも滅多にない。酔う前に眠ってしまうのである。
それがこんなに「酔っている」ということは、普通のことではないのだ。
キングが悲鳴を上げた。
「舞、悪いけどユリの話し相手になってやってよ。私は、どうもこういう話は苦手なんだ」
舞に向かって肩をすくめてしまう。
本当に今日は、つくづく珍事に恵まれた日だ。まさかキングが弱音をはくとは。
「それはいいけど……」
舞は困ったようにユリに目を移した。こんな状態のユリから、まともに話が聞けるのかどうか。
当のユリはうなるような声で、
「ユリの話が聞けないのかよぉー」
などと、キングにイチャモンをつけている。まったくもって迷惑な客である。
舞は自分も軽めのカクテルを一つ頼むと、ユリに優しく語り掛けた。
とにかく、何があったのか聞かなければ何も始まらない。
「それで、なにがあったのよ、ユリちゃん」
舞の声が耳に届いたのか、ユリはぐりん、と首を回して舞を据わった目で
その異様さに、思わずびくりと舞は肩を震わせた。
ユリの口から、アルコール成分を多量に含んだ吐息がもれる。
少しうなじを見せながらしどけて見せれば、子供っぽさの抜けないユリでも十分に艶やかな情景であったろうが、残念ながら今日のユリは、ただの酔っ払いである。
色っぽさなどかけらもない。
「舞
それを、下手に出てりゃ、あの女〜!」
なんとも思っていないどころか、明らかに含むところがあるような声で、ユリはぶちぶちと文句を続けながら、グラスのカクテルをぐいっと呷る。
それにしても、普段、ユリは自分のことを「私」とか「あたし」とか言うが、子供の頃は「ユリ」と名前で呼んでいた。
子供の頃の癖が蘇るほど酔っているのか、酔ったら癖がぶり返すのか。
舞には分からない。分かるのは、ユリが自分の限度量を超えて酔っている、ということだけである。
「はいはい、それで、その女の人ってのは誰で、その人がどうしたの?」
ユリの話はあっちに飛び、こっちに飛び、七転八倒してスタート地点に戻ったりと、なかなか要点を得なかったが、舞は根気よくユリの話を聞いてやる。
しかしてユリの文句の源は、やはりというか舞が予想していたとおり、ユリの兄、リョウのことであった。
しかし、いつもと状況が違うのは、リョウ本人への文句だけではない、ということである。
リョウに女性の影が見え隠れしていたのだ。
創業者一族であり、広告塔でもあるサカザキ家の存在感が大きいため、あまり認知度が高いとはいえないが、極限流の道場は現在、完全な「一族経営」からの脱却を果たしている。
様々な大会での活躍や、なかば破壊的ともいえるPR活動の結果、道場生の増加と道場の規模の拡大に伴って、道場で働く、いわゆる裏方のスタッフの数も驚くほど増えていた。
特に、サカザキ家には経理関係が分かる人間がいないので、懇意にしているイタリアのガルシア財団から専門家を招いて経理部門を委託している。
……の、だが。
この「専門家」が、ユリの不満の元となっているのである。
オーガスタ・ジュールズという名のその女性は、確かにやり手であった。
ケンブリッジ大学出身の才媛で、数字に強い上に頭の回転が速く、さらに女性ならではの細やかな企画力を発揮したりと、サカザキ家では目の届かない能力を全て持っている、と言っても過言ではない。
それだけに、当初は道場主のリョウも全幅の信頼を置いてた。
が、彼女が派遣されて半年ほど経ったあたりから、段々とオーガスタの態度が変化をみせ始めた。
もちろん、仕事は真面目にこなすのだが、やたらとサカザキ家のプライベートに割り込もうとしてくるようになったのである。
きっかけは些細なことだ。ある一日、リョウがオーガスタを夕食に誘った。
それは、大変な量の仕事をこなしてくれる彼女への感謝の意味であり、それ以外の意味も、それ以上の感情も全くなかったのだが、どうやらそれが「過ち」であったらしい。
ミス・ジュールズのリョウへの態度は、それまでのビジネスライクなものから一変した。(ユリから見れば)急に馴れ馴れしくなったのだ。
リョウとユリの日課である早朝のランニングに同行するようになり、週末にはリョウを食事に誘うようになった(リョウが応じる可能性は三分七分、といったところだったが)。
ユリにとってわけがわからないのは、この才媛ミス・ジュールズが、やたらとユリに敵対心を燃やしていることだった。
それまでは、例えば早朝のランニングにしても、夕食の買出しにしても、リョウとユリが連れ立っていくことが日課になっていた。
いわば習慣のようなもので、ユリにとってもリョウにとっても自然なものであったのだが、オーガスタはそういうところに好んで割り込んでくるのである。
そして、リョウが見ていないところで、ユリにこう言うのだ。
「ユリちゃんとリョウさんって、本当に仲がいいのね。私は一人っ子だから、なんだか羨ましいわ。いつまでもお嫁さんみたいに甘えられるお兄さんが、私も欲しかったわね」
言葉だけならば、本当に羨望していると受け取れなくもないが、当のユリにとっては、かなり強烈な皮肉だった。
「早くお兄ちゃん離れしちゃいなさい」
オーガスタは、わざと分かるようにそう言っているのである。
一方で、ユリは道場の中でちゃんと師範代の仕事もしているし、そこまでリョウに依存している意識などない。自覚のない身にとっては、当てこすりもいいところだった。
オーガスタがリョウを狙っていることは、ユリも気付いていたが、そんな女性から、なぜ妹の自分が攻撃対象にされなければならないのか。
だがオーガスタの心理攻撃はことあるごとに笑顔で繰り返された。ユリとしては反論してもみるのだが、頭の回転の速さでも舌の回転の速さでも、残念ながらオーガスタには勝てず、いちいち論破されてしまった。
そのたびにユリは、
「成人も近いくせに兄離れできない甘えん坊の妹」
などと決め付けられてしまうのだ。
かといって、唯一彼女に勝てそうな腕力と体力に安易に訴えるわけにもいかず、結局はヤスリで削られていくような精神と、キリキリと痛む胃の両方を抱えもって、ストレスを貯めるしかなかったのだ。
ユリは物理的・金銭的な困窮にはいくらでも耐性があったが、逆に心理的な攻撃に対しては脆い。それは、これまでリョウという厚い壁に護られて育ってきた、ということの裏返しであり、それを自覚しているから、極限流空手を身につけて、身も心も強くあろうと「強がっている」のである。
ユリにその意志さえあれば、ミス・ジュールズの「嫌がらせ」をリョウに訴えることもできる。そうなれば、リョウがユリの苦心を見逃すはずもなく、即座にミス・ジュールズに対して何らかの行動に出てくれるだろう。
だが、それはユリにはできなかった。「しなかった」のではなく、「できなかった」。
まず、リョウに心配をかける、ということ自体が嫌だった。ユリはリョウに心配をかけたくなくて、極限流空手を習ったのだ。それが自分から弱音をはいていては、まったく意味がないではないか。
それに、もしもこれが原因でミス・ジュールズがガルシア財団に送り返されるようなことにでもなれば、今度は彼女をリョウに推薦したロバートの面目を潰すことになるだろう。
ユリにとっては、それも耐えられることではなかった。
どちらにしても、ユリが自発的にできることは、ひたすら我慢することだけだったのである。
……が、その沸点もついに限界が来たようであった。
(To be Continude...)
(初稿:09.07.07)