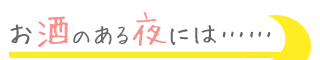

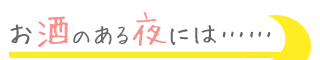

イギリス、ロンドンの一角に、若い女性に人気のある「イリュージョン」という名のバーがある。
そう特別に広いと言うわけではないし、特別に安いというわけでもない。
だが、小洒落たセンスに、種類の多いカクテル、更にマスターが頼りがいのある若い女性だということも手伝ってか、ここには多くの男女が常連として通っている。
たまにこの店は、マスターの顔なじみという客限定で、正規のクローズ時間後に店を開けることもあった。
今のお客も、そういった類の客だ。
マスターは、若い女性格闘家としても知られる本名不明の麗人、キング。
客の名は、リョウ・サカザキ。
「すまない、まだ、飲めるかな?」
言いつつ、しっかり【CLOSED】の看板をかけてあるドアを開けて入ってきた客に、グラスを拭いていたキングは、苦笑いしながら応対した。
「あんた、解って来てるくせの第一声じゃないね」
「そうか、すまんな」
微妙に会話が成立していない。だが、マスターも客も、あまり気にしていないようである。
「まぁ、いいさ。あんただって、明日がここの店休日だって知って来てるんだろうから。
特別に、一杯くらいは作ってあげるよ。オーダーは?」
「そうさな」
薄いスポーツシャツにジーンズという、場違いとも言えるラフな格好をしたその金髪の男性客は、慣れた口調でオーダーした。
「“いつもの”をいいかな」
「“Closed Hope”か。わかったよ」
それはその客、リョウ・サカザキのためにキングが誂えた、オリジナル・カクテルの名だった。
リョウがキングのバーを訪れるのは、妹のユリと比べると少ないが、絶無と言うわけではなかった。
ただ、リョウにしてみれば理由がないと来辛い場所ではあるのか、何かしら来るたびに話の種を持ってくる。
キングも半ばはそれが楽しみで、いつも突然やってくる、この“戦友”の訪問を邪険にすることはなかった。
無論、二人ともそれ自体が“口実”だということはじゅうぶん理解しているが、それを口にするほど、二人は幼くもなければ、素直でもない。
「で? 今日はなにがあったんだい」
プロの手つきでカクテル・シェイカーを振りながら、いつもの如く、キングの方から話しかける。
店の中に二人しかいない時の、いつもの風景であり、返答もだいたい決まっていた。
「ま、ユリのことではあるんだがな」
キングの手つきを、何故だか嬉しそうに眺めながら、でも困ったような口調で、リョウが言葉を返す。
「またケンカでもしたのか? まったく、仲が良いんだか悪いんだか、解らない兄妹だね」
呆れたように言いながらキングがグラスをリョウにさし出すと、リョウはゆっくりとそれを受け取り、一口だけ口に付けてから再びカウンターに置いた。
「いや、今回のケンカの相手は俺じゃないよ」
「? タクマなのか」
「ロバートだ」
「ロバート?」
キングが、不思議そうな顔をする。
さもありなん。ユリは普段の明るさからは信じられぬほど恋愛には奥手だし、ロバートはユリにどこまでも惚れこんでいるが、マナーは守る男のはずだから、あまりケンカになりそうなカップルではないのだが。
「ケンカにしては珍しい組み合わせじゃないか。なんだかんだ言っても、あの二人が一番ケンカとは縁遠そうなんだけど」
「そうだな、俺もそう思うよ。
だがまぁ、あの二人も付き合いが長いからな。たまにはケンカもするだろうが……」
リョウは不自然に言葉を切り、カクテルを煽る。
ユリとロバートの面識は、リョウたちが六歳の時からだから、それこそ十年をゆうに超える。
どちらかと言えば熱烈な恋愛エピソードというものは少なく、幼馴染みの延長、という印象がどこまでもあるのは、お互いの初々しさのせいなのだろうか。
「なるほど、ただのケンカじゃ終わらなかったわけだ」
その不自然な言葉回しから、大抵のことを悟ってしまったのだろう。キングは、腕組みをしてカウンターに体重を預ける。
完全に、興味本位で話を聞こうという体勢である。リョウもそれを察しているから、というか、最初からそれを話しに来ているのだから、さほど慌てることもない。
「ああ、ありゃあヒドかった。ユリが、えらくヒステリックになってな。
ロバートもヒートアップしちまって、口論した挙句に、肉弾戦に突入だよ」
肩をすくめてリョウは苦笑したが、キングは意外さを隠さなかった。
「ヒステリー?
「そう、
「で、その後はどうなったのさ」
「そりゃ、お互いに実力行使さ。道場まで行ってから、ま派手だったぜ。
最初のあたりは、まだお互いに遠慮があったんだけどな。覇王翔吼拳が相打ちになったあたりから二人ともキレちまったらしくて、最後は飛燕鳳凰脚と
ばぁん、と、リョウはオーバーアクションで相打ちを表すと、くはは、と彼らしい苦笑いをした。
聞く方のキングは目が点である。
ユリとロバートがお互いに対して超必殺技を打ち合うほど「キレる」というのも意外だが、それを、他の誰でもないリョウが、こうして苦笑しながらも微笑ましく語る、というのもまた意外だった。
「はぁ、そりゃあまた、難事だったんだな……」
「まぁな。恐がって誰も近づけやしない」
「そりゃまぁ、そうだろうねぇ。
なにせ、道場責任者のあんたが、わざわざ
「はは、そりゃ違いないな」
シニカルな笑顔を見せたキングに対し、リョウは苦笑して応えた。
もちろんリョウは、しっかりとそのケンカの事後を処理しているし、別の重要な用事があって地球を半周しているのだが、そんなことは二人にとっては確認するほどのことでもなかった。
「でもさ、私が意外なのは、アンタのほうだよ、リョウ」
「俺が?」
「だって、そうだろ。可愛がってる妹が、恋人と命がけのケンカしたってのに、随分余裕があるじゃない。
アンタならもっとこう、ガーって怒ると思ってたんだけど」
「……いや、“ガー”って、お前ね」
半ば本気で驚いているキングに、困ったような表情を浮かべた。
「そりゃあ、俺だって心配はするよ。だけど、ユリももう18だ。じゅうぶん大人の年齢さ。
ユリにはユリのプライベートもあるし、生き方もあるだろ。いちいち俺が口を出すことじゃないさ」
カクテルの最後の一口を飲み干し、呟いた。
「アイツが考えて、アイツが決めることだ」
「へぇー……」
キングが、腕を組んで頷く。感心しているようでもあり、驚いているようでもある。
「なるほど、それがサカザキ家の教育方針ってわけだ」
「そんなご大層なモンでもないけどな」
リョウはちょっとだけ苦笑を閃かせたが、すぐに大人の笑顔に戻る。
そして、空になったグラスを脇に避け、彼も腕を組んだ。
「そうだな、キング。こういう話はどうだ。
お前も、俺と同じようにジャン君を育ててきたわけだが」
「ああ」
話のポイントが変わったことを悟って、キングは少し背筋を伸ばした。
「お前や俺が生きていたような環境の中でジャン君を育てるのに、お前が一番気をつけたことはなんだ?」
腕を組んだまま顎に指を当てて、少し上を向いてキングは考える。
この男装の麗人が思考を進めるときの、無意識の癖だった。
「そりゃあ……、せめて人並みの生活をさせてやることだろうね。
同年代の友人に帰る家も案内できないんじゃ、余りにも不憫だし……」
そう、リョウもキングも、ただお互いの幼い妹・弟のために命がけで戦い続けて、今の地位と生活を築いたのだ。
リョウの質問は続く。
「じゃあ、ジャン君本人に対しては?」
「一通り常識は教え込んだよ。
なにをしてはいけないか、とか、生きるためには何が大事なこととか。
あくまで、育ての親って役割の中でできることだけど……」
言いかけて、キングは何かに気付いたようにリョウに視線を向けた。
「ま、そういうことさ」
教師が出来がいい生徒の顔を見るような表情で、リョウは頷いた。
「一通り教えることを教え込んだら、俺たちがあいつらにしてやれることは、本当にしてはいけないことをした時に怒ることと、あいつらが挫けた時に帰るべき家を維持しておいてやることと、それだけだろ?」
どう足掻いたところで、彼らは【育ての親】という立場を超えることが出来ない。
いくら弟や妹を心配し、教育し、育てたとしても、それが【生みの親】がしているのものと同じ意味でできているのかどうか。
彼らには、常にそういった種類の【劣等感】が付き纏う。
いくら命がけで戦い、荒金を稼ぎ、弟妹の生活を保障していても、その弟妹が
「なんで私たちにはお父さんやお母さんがいないの?」
と泣きだしたら、彼らにはどうすることも出来ないのだ。
無論、キングはユリがリョウに、リョウはジャンがキングに、感謝してもしきれないくらい感謝し、自分の兄姉を尊敬していることを知っている。
だが、それが自分のこととなると、少なからず自信を欠いてしまうことは確かだったのだ。
だからリョウは、ユリには彼女がやりたいことをやらせた。
褒めるべき時は褒め、怒るべき時は怒る、と、しっかりとメリハリをつけることで、タクマが戻った今も、父親としての役割を果たそうとしている。
普通の父親と少し違うのは、最低限の常識と、自分の道を決めるために知識と経験を得ることが大事だと教えた後は、リョウが決して自分の価値観をユリに押し付けなかったことと、ユリの生きるべき道を強制しようとしなかったことだ。
ユリにはユリの道がある。自活できる能力がユリにつけば、あとリョウに出来ることは、彼自身が言明したように、妹が挫けた時に路頭に迷うことが無いように、帰るべき場所を守っておいてやること、それだけなのだ。
だが、彼は段々とユリが自分の手を離れていっていることにも気付いており、小さな寂しさも感じていた。
それが、生みの親が持つ寂しさと同質のものであるということに彼が気付くのは、彼自身の娘が巣立つ、もう少し未来の話となる。
そして、それはキングの過去や生き方とも通底することだった。
だからこそ二人は、全てを語らなくても分かり合える“戦友”となりえたのだった。
「……ああ、そうだね」
全てを理解してキングは少しだけ微笑むと、リョウの言葉に、小さな声で頷いた。
「さて、一杯だけという約束だし、これで失礼するかな」
一通り談笑したあとで、壁に架けられた年代物の時計が23時をさしていることに気付き、リョウは立ち上がった。
キングも彼を止めない。この夜は最後かもしれないけれど、また幾ヶ月か経てば、この男はふらりとこの店にやってくる。
そのことを彼女は【知っていた】から。
「ホテルはとってるんだろ。どこだい?」
「いつものところだよ。ソーホーの安宿さ」
キングは、リョウがロンドンで常宿にしているそのビジネスホテルが、一泊20ポンドで宿泊できることを知っていた。
「なんだ、倹約家ぶりは相変わらずだね。そう金に困るような生活をしてるわけでもなかろうに、身についた金銭感覚は抜けないか?」
「貯めこんだって、使い道を知っているわけでもないしな。それに【倹約家】ぶりはお互い様だろう?」
リョウが言うと、キングは苦笑し、彼女らしい表現で肩を竦める。
「ふふ、そういうことにしておこうか」
それじゃあな、と、リョウは背中越しに手を振り、イリュージョンを後にする。
キングも、それじゃあね、と背中越しに一言だけ返し、店に戻っていった。
肉体的に繋がることだけが男女の絆を約束するものではない、ということを意識せずに理解している一点において、この二人は、周囲の誰よりも大人の関係を維持しているのかもしれない。
ちなみに、ユリとロバートのケンカの原因が「テレビのチャンネル争い」だった、ということを知ったリョウに、この二人がキツい拳骨を一発ずつ貰うことになるのは、また別の話である。
(Fin)
私は、どちらかというとリョウとキングには、ベタベタとくっつくのではなく、クールでシニカルな付き合いをして欲しいと思っているのですが、公式がなぁ(笑)。
考えてみれば二人とも(KOFでは)24歳。恋愛もまだまだ若気の至りで通用しそうな年齢ですが、過去の設定を考えると、二人とも直前で立ち止まって、結局は冷静な視点で交流をしてしまいそうな気がします。
……いや、私はリョウ×香澄派なんだ、そういえば(笑)。
恋愛感情で落ち着くのではなく、共通の経験を下敷きにしているがゆえに落ち着ける。そんな男女の関係があってもいいかもしれません。
(初稿:08.05.10)